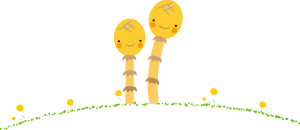2025年12月号
熱かった!暑かった!の今年も、とうとう12月最後の1枚になったカレンダー。秋を十分に楽しむ間もなく、初雪を迎えました。前にも書きましたが、季節が少しずつ移りゆく様を「四季」としてきましたが、近年は「二季」になっているのでは、と言いました。先月発表された「流行語大賞」の中に「二季」があったのを見て、やはり多くの方々がそう思っているんだと思いました。
さて、12月はみんなが楽しみにしている「クリスマス会」もありますね。今、3園の子どもが練習に励んでおります。子ども達は一生懸命ですが、先生達も一生懸命です。小さいお友達は、必死に動いたりうたったりする先生を初めは不思議そうに見ていますが、だんだん同じように動くようになります。動かない子もいますよ。大きい子になると、自分たちで振付を考えてみたり役を選んだりして、自主的に参加をしていきます。ひかり組さんは「降誕劇」を行います。役は自分で選びますが、てんしをやりたい子、博士をやりたい、星の子をやりたいと普通思いますが、意外にも人気があるのは「宿屋の主人」なんです。何故なのかなと思うと、この劇の中で扉を使って出入りするのは宿屋の主人だけなので、子どもに人気があるんです。各クラスみんな頑張って練習しています。どうぞ、前日の12日はおばあちゃん・おじいちゃん、地域の方々に観ていただき、13日は保護者の皆様に観ていただきたいと思います。ぜひ参加していただき、大きな大きな拍手を送ってあげて下さいね。
次はお願いになります。
かねてより、食材の値上げは止まることを知らず、財政面ではかなりの負担になっております。今年も何かと赤字だとか、米がまた上がる、乳製品が上がる、とこのおたよりを通して言ってきました。皆さんの家庭も大変だと思うので、何とか給食費の値上げをしないで頑張ってきましたが、正直このまま値上げが続くのであれば、給食費を2026年4月より、1人500円の値上げをさせていただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。1月末から2月上旬までには、はっきりしたお知らせをいたします。
次は「からだっていいね」の実施状況ですが、11月で3回終了していますが、子ども達の反応も大変良いようで、菱沼先生には感謝しています。又、参加される保護者の方は数少ないですが、参加していただき良かったと思っています。乳幼児期の性教育は、よく新聞(とりわけ朝日)に掲載され、その重要性は社会問題になっており、子ども達を性被害から守るためにも、少しずつでも続けて行きたいと思っています。11月29日(土)には、保育担当する以外の全職員による「からだっていいね」の研修を受けることになっております。
合わせて、いよいよ2026年4月から「こども園」になりますので、そのことでは主任、園長等が何かと多くの研修を受けてきましたが、12月13日のクリスマス会後、全職員の研修を予定しております。何かと家庭保育のご協力をいただくと思いますが、ご協力いただけると助かります。
今年も、暑さ対策に追われた感がありましたね。でも、大きな怪我や事故もなく、健やかに子ども達は育ってきたと思います。最近は、インフルエンザの流行を心配していましたが、大きな流行とまではいかず、このまま新年を迎えられたらと願っております。
今、子ども達はクリスマス会の練習の合間は外に出て、風に吹かれる落ち葉を追いかけたりしながら、元気に遊んでおります。
・12月21日(日)クリスマス礼拝 (10時45分から)
・12月24日(水)イヴ礼拝 (午後7時から)
が鶴ケ谷教会で行われます。よろしければどうぞご参加下さい。
最後になりますが、子ども達も保護者の皆さんもこの年末どうぞ健やかに元気でお過ごしください。
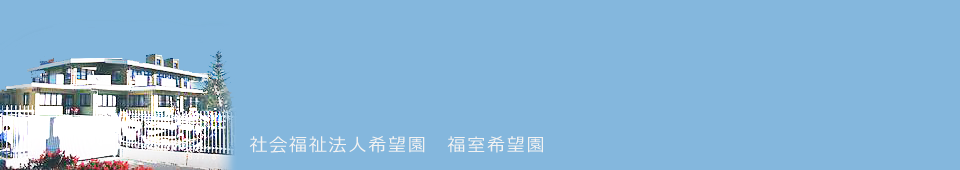
 福室希望園の園長、髙野幸子先生です。
福室希望園の園長、髙野幸子先生です。